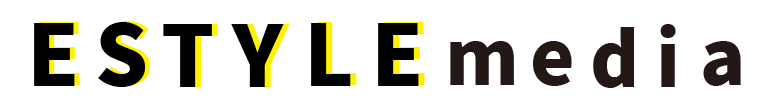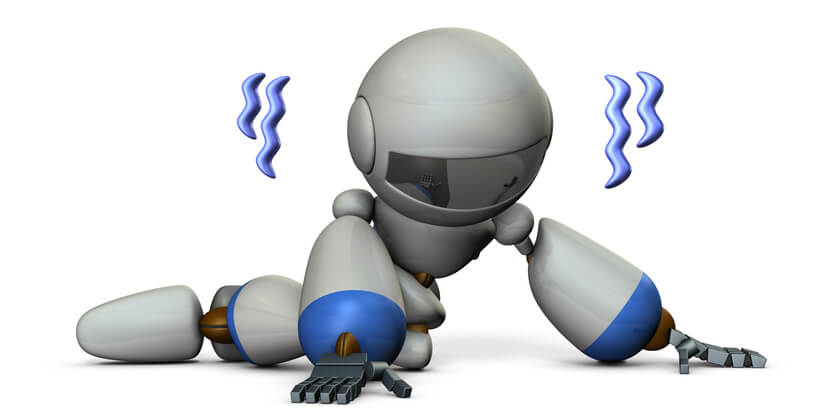IT人材は、日本全体で人手が不足しています。
2019年度の独立行政法人情報処理推進機構(IPA)によると、IT人材の量について、「大幅に不足している」「やや不足している」という回答の合計は、89.0%にも達しているとの結果が分かりました。
IT人材のなかでも、AIエンジニアはまだまだ不足しており、需要が高い業種です。
ただ、人手不足ではあるものの、AIエンジニアになるのは難しいといえるでしょう。この記事では、AIエンジニアになるのが難しい理由について解説します。
AIエンジニアは不足だが転身が難しい

人材が不足しているなら転身のチャンスと思うかもしれませんが、AIエンジニアに転身するのは難しいでしょう。その理由は2つあります。
- 企業側がどのようなAIエンジニアを採用すれば良いのか判断が難しい
- AIエンジニアに求められるスキルが高く習得が難しい
前者は、企業目線から難しいと考えられるものです。AIエンジニアのスキルは難しいものが多く、AIに対しての理解が浅いため、採用する側もどの程度のスキルがあれば良いのか判断できないケースが多いです。
明確な採用基準を持つのが難しく、思うように採用できないことがAIエンジニアへの道を難しくしています。
後者は、純粋にAIエンジニアに求められるスキルが高い点です。AIと聞くと、最新の技術のため「なんでもできる」と思われがちなので、他のエンジニアよりも結果に対してのハードルが高い傾向があります。
AIエンジニアになるためのスキルの取得が難しい

AIエンジニアの必要スキルは以下のようなスキルが挙げられます。
- AI開発のプログラミング
- 数学的な知識
- データ解析
- 機械学習アルゴリズムやディープラーニング
では、それぞれどのように取得が難しいのか見ていきましょう。
AI開発のプログラミング
AIを開発するにあたって、プログラミングができなければなりません。
多くの言語で開発されていますが、最近では「Python」を中心に「C」「java」などがプログラミング言語に多く採用されています。
これらのプログラミングスキルがなければ開発はできません。
数学的な知識
AIエンジニアは、数学的な知識がなければなりません。
これがなければAIの仕組みを理解するのは難しいでしょう。高校で学んだ微分や積分、確率統計などの知識をベースとして、さらに難易度の高い数学を扱えなければなりません。
データ解析
AIエンジニアは、データ解析に関するスキルも求められています。
数学的なものと重なる部分はありますが、ここでは独立して考えましょう。最近耳にする言葉では「ビックデータ解析」と呼ばれるものがここに該当します。
機械学習アルゴリズムやディープラーニング
AIエンジニアは、機械学習アルゴリズムやディープラーニングに関するスキルも必要です。
AIは機械学習アルゴリズムを利用し、機械学習アルゴリズムはディープラーニングを利用しています。そのためAIを開発するにあたりこれらの知識も必要です。
なぜAIエンジニアになるのは難しい?課題と難易度
AIエンジニアになるのが難しい理由は、スキルの取得だけではありません。AIエンジニアは課題と難易度の面でも難しいといわれています。
その理由を見ていきましょう。
AIの学習が複雑で勉強しにくい
AIエンジニアは、AIエンジニアは機械学習や統計学を使ってデータを分析したり構築する必要があります。
そのため、知識がないとデータを適切に扱うことが難しく、問題解決を行うことができないため、AIエンジニアに転身する前に自己学習を進めなければいけません。
例えば、AIの開発などに必要な機械学習アルゴリズムやディープラーニングなど基本的な考え方も難しく、ここでつまずいてしまう人もいるぐらいです。
ディープラーニングは機械学習アルゴリズムの一つであり、データを読み込ませることでさまざまなことをAIに学習させていきます。
ただ、読み込ませるデータを間違えると意図した結果を得られないという問題点があるため、AIを開発するまで深く理解するのは難しい部分でしょう。
数学的な素養が必要
AIエンジニアは、情報を数学的に解析するため数学の素養も必要です。多くの場合は数学的には有名なアルゴリズムが利用されます。
理解するべき数学のアルゴリズムは多数あります。一例を挙げるとすれば、以下のアルゴリズムを理解しておくと良いでしょう。
- k近傍法
- k平均法
- 決定木
- ランダムフォレスト
- SVM
- マルコフ連鎖
これらの中には数学の素養があれば、理解しているものも含まれているかもしれませんが、知らないものは自分から学ぶ必要があります。
学習状況は人それぞれですが、これらの数学的な素養がAIエンジニアになることを難しくしています。
めまぐるしい技術進化である
AIは技術が高速で進化しています。
AIに限らず、ITは全体的に技術進化が高速である業界で、1年前に開発された技術がすでに利用されていないこともあるぐらいです。
これは極端な例ですが、3年もすれば新しい技術に置き換わることが多々あります。
加えて、AIは1年間で多くの技術が生み出されることも十分にありえます。実際、生成AIを使った画像作成や音声作成はめまぐるしい速度で進化していると感じるでしょう。
これからAIエンジニアを目指すのであれば、学習しているうちに新しい技術が生み出されます。つまり、技術を習得しても徐々にゴールが遠ざかってしまうのです。
学ぶ内容だけではなく、内容量が徐々に多くなり続けることもAIエンジニアになることが難しい理由です。
論理的な思考が必要
AIエンジニアには論理的な思考が必要です。
AIエンジニアはデータサイエンスなど機械学習アルゴリズムを使いこなせなければなりません。ここは論理的な思考が必須です。例えば各種数学的なアルゴリズムやデータ構造の理解が必要です。
また、物理的なアーキテクチャに関しての理解も必要です。これらを使いこなすのにも論理的な思考が必要です。
日頃から意識して論理的な思考を持つことに慣れなければならない点でも難しいものです。
AIエンジニアに向いている人の特徴
上記の内容を踏まえて、AIエンジニアに向いている方の特徴です。
- AIのプログラミングに興味がある
- AIの複雑な概念にも興味が持てる
- 数学的なアルゴリズムに興味を持てる
- 論理的に考えることが好き
- 技術進化の速さにも耐えれる
AIエンジニアは、最適なモデルが出来上がるまで何度も仮説検証や分析を行ったり、スクリプトを作成する際にエラーを吐き出してしまったりと、根気が必要な仕事です。
よって、業務自体が楽しいと感じなければ難しいかもしれません。
AIエンジニアへの転身で挫折しないための心構え
AIエンジニアへの転身は挫折する可能性も考えられます。AIエンジニアの業務が難しく、作業時間が長引く日が続くと途中で心が折れてしまう可能性もあるでしょう。
AIエンジニアの職に就いたあとに、そうならないために、心構えについて解説します。
①物事を論理的に考えられる人間になる
まずは、物事を論理的に考えられる人間になることを意識しましょう。
データサイエンスなどAI業務は論理的な考え方が必要です。逆に論理的ではなく感情的な考え方をするとAIエンジニアとしての活躍は難しくなるかもしれません。
論理的な考え方を持つには慣れが必要です。まずは結論から考え、それが正しいかどうかを深掘りしていくような思考を持ってみるとよいでしょう。
②AIエンジニアの仕事を美化しすぎない
AIエンジニアを目指す人の中には、「AIエンジニアはすごい仕事である」「私はすごい仕事しかしたくない」などの意識を持つ方も珍しくありません。
確かにAIエンジニアは難しい仕事であり、誇りを持てる仕事には間違いないですが、中途半端な気持ちでAIエンジニアを志すと、スキルとのギャップに絶望してしまう可能性もあります。
AIエンジニアの技術的な内容に興味を持てる方や、学習意欲が高く新しい情報にも熱心な方など、AIエンジニアになったあとも学習を続けられる方が向いているといえます。
③AIエンジニアになるのは難しいと自覚する
AIエンジニアは求められるスキルが高いので、AIエンジニアが不足している現在でもなれる方は少ないです。
「AIエンジニアは人数が少ないため余裕」「AIエンジニアはかっこよさそう」などの生半可な気持ちでAIエンジニアを目指すと転身に失敗してしまう可能性もあるでしょう。
AIエンジニアになるのは難しいと自覚して、高い学習意欲で取り組むことでさまざまな壁にぶつかっても乗り越えられるでしょう。
また、AIエンジニアは長期的に同じプロジェクトに取り組むケースが多いので、根気も大切です。十分に心構えを持ってからAIエンジニアへの転身にチャレンジしましょう。
エスタイルでは未経験からのAIエンジニアを募集!
「未経験からAIエンジニアにチャレンジしたい!」という方は、エスタイルにご応募ください。
エスタイルは未経験からAIを使った業務に就いたメンバーが9割以上と、ほとんどが未経験からのスタートです。また、未経験でAIエンジニアになった方もいます。
エスタイルでは、最短2ヶ月の導入研修を行っているので、入社後もAI・データサイエンス人材として必要なスキルを習得できるのが特徴です。
オンボーディング担当メンバーのサポートもあり、AIエンジニアとして確実にスキルアップできる環境を整えているため、学習意欲がある人であればどんどん成長することができます!
AIエンジニアの募集要項
エスタイルのAIエンジニアの必須条件を紹介します。転職の参考にしてみてくださいね。
- 大学院(修士・博士)卒・修了見込みの方
- 以下いずれかに該当する方
学生時代に理系の学部・学科を専攻をされていた方で数学(線形代数・微積分)が得意
機械学習(画像・自然言語・構造化データ)、Deep Learning、LLMのいずれかに関する知識・知見がある(独学OK)
また、読み書きレベルの英語を取得している方や、英語の文献や論文を扱える方もAIエンジニアとして活躍できる可能性が高いです。
ぜひ、ご応募お待ちしています!
▼エスタイルの業務や環境が知りたい人はこちらも参考にしてみてください!
AIエンジニアの基本的な情報や身に付けるべきスキルは、以下の記事で詳しく解説しています。